�����N�Ɩ��C�ށi�P�j�L�@���Ɨ���
���@���ƗL�@��
���{�͌o�ς̍��x�����Ƌ��ɕ�炵�����ς��A
�����⍇������Nj�����ߒ��ŐH�i�͎��肩�烌�g���g�ցA
�ߗނ͖ȓ����牻�@�ւƁA�H�ƕi�ɒu���������܂����B
�Z�����O�ł͂���܂���B
�ؑ��Z��Ŗ��C�ނ���A���@��F�����Ǘ����₷�����A
�������鑤�̓s���ōH�ƕi���g����悤�ɂȂ�܂����B
�V�b�N�n�E�X�nj�Q���Љ�ۉ��������A���N�Œ���������Ƃ����߂��Ă��܂��B
�������͂��̋����҂Ƃ��āA�Z��̂�������������K�v������ƍl���Ă��܂��B
���Ђł́A���q�l�Ɉ��S�E�[�����Ē�����悤�A
�g�p���Ă���f�ޓ��̐����A�J�^���O�ł͂Ȃ��Ȃ��킩��ɂ����Ƃ̕��͋C
�Ȃǂ�m���Ă����������߂��V�����n�E�X�c�A�[�E���������J�Â��Ă��܂��B
�֗��ɂȂ�l�ԂɊQ���y�ڂ����̂��o����Ă��鐢�̒������炱���A
���N����Ԃɍl���������̂ł��B
���ł����A�����҂����Ă���܂��B
|


|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�Q�j�t�B�g���`�b�h
�t�B�g���`�b�h
�N�����Ă��钎��ۂ���g����邽�߂ɁA��������o���Ĕ��U���Ă��镨���ł��B�̍����F�Ȃǂ̂��ƂɂȂ鐬���ł��B
���̃t�B�g���`�b�h�́A�ۂȂǂ����ނ��铭���������܂����A
�l�ԂɂƂ��Ă���������������A�����_�o�����肳����A�Ȃǂ������������炷���ʂ�����܂��B
�}�c��q�m�L�Ȃǂ��j�t���̓t�B�g���`�b�h�̔��U�ʂ������A�Ɖu�͌���ɂ��𗧂��Ă����̂ł��B
���{�l�ɂƂ��Ė����̋�Ԃł��邨���C�B�����ő̂����߂邱�Ƃɂ������ƁA�q�m�L�̍���ɂ�郊���b�N�X���ʁB�̂���A�q�m�L���C��������Ă��闝�R�͂����ɂ���̂�������܂���ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�R�j�̌ċz
�u�͌ċz�����Ă���B�v�ƕ��������Ƃ�����Ǝv���܂��B
����Ă��܂����琶���Ă��Ȃ��̂ł́H�Ə���������^��Ɏv�������Ƃ�����܂����B
���������鏊�Ȃ́A�����������C�ނ͎��R�Ɏ��C�̋z���E���o���J��Ԃ��A�����̎��x��50�`60���ɒ������Ă��܂��B
�����̒����������Ă����Ԃł́A�̒��Ɋ܂܂�Ă��鐅����f���o���ďk�݁A
�t�Ɏ��C�̑����Ƃ��ɂ͗]���Ȏ��C���z�����Ėc��ށB�܂��ɐl�Ԃ̌ċz�̂悤�ł��ˁB
����́A�؍ނ̑@�ۂ̋�C�̑w���e�����Ă��āA�L�t���Ȃǂ̌�����������A�j�t����˂Ȃǂ̏_�炩������̂ق����D��Ă���̂ł��B
���C�ނ͒������ʂ�����Ă��邽�߁A�A�����M�[�Ǐ�̂��������ł����錋�I��}�������������܂��B
�����ŁA���Ђł͂��q�l�Ɉ��S�E���S�����͂����邽�߂ɖ��C�ނ��g�p���Z��Â�������Ă���̂ł��B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�S�j����
�����I�E�S���I����
�A�S�A�R���N���[�g�A���ꂼ��ō��ꂽ�O��ނ̃x���`����������A�قƂ�ǂ̐l���ؐ��̂��̂ɍ����|����ł��傤�B
�S��R���N���[�g�A�₽���v���X�`�b�N�ȂǂɐG���ƁA�l�͂�����X�g���X�Ɗ����������㏸���܂��B�ɐG�ꂽ�Ƃ��͂��̂悤�Ȕ����͋N���܂���B
�؍ސ��i���g�p����Ă���I�t�B�X�ł́A�K��҂��]�ƈ��ɑ��ĕ�������ۂ��A
�ʏ�̃I�t�B�X�Ɣ�D�܂�����ۂ�^����Ɠ����ɁA
�]�ƈ��̎d���̌��������A�b�v���A��������ӔC���A�M���������܂���
�Ƃ���������܂��B
���{�݂ł́A�؍ސ��i�����������ƁA�����ғ��m�̃R�~���j�P�[�V��������͂ւ̔F�m�͂����܂�܂����B
�����ɖ؍ނ��g�����ƂŁA�����݂�����S�n�悢���߁A�����w�I�ɂ��S���w�I�ɂ��|�W�e�B�u�Ȕ����������̂ł��B�O���I�A�����I�X�g���X���������ゾ���炱���A�̉����݂������ꂽ�����̂ł��ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�T�j�h�A�ƈ�����
�h�A�́A�����˂Ɣ�ׂċC�����Ƃ�₷���\���Ȃ̂ŁA
�g�C����h�����Ɏg���C���[�W������܂��B
�ŋ߂ł́A�����̊��C���m�ۂ��邽�߂ɃA���_�[�J�b�g���Ă�����̂������ł����A
���̏ꍇ���Ɩh�����͈����˂ƕς��܂���B
���̓_�����˂́A�J�̓r���Ŏ~�߂ĊJ������ł��邱�Ƃ���
�ʕ����Ƃ�₷���ł��B
�X�y�[�X���Ƃ炸�Ɉړ��ł��A�Q���A�R�����������߂Ή����ɂ��J�������܂��B
�����˂́A�h�A�ɂ͂Ȃ������݂��������܂��ˁB
���́A�h�A�����ȂǂŐ����悭���܂鉹�ɂ悭�т����肵�Ă��܂��̂ň����˂̕����D�݂ł��B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�U�j���Ԃ̒��S
���Ԃɂ͎������W�߂钆�S�����܂��B
��ȃf�U�C���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�Ӑ}�I�Ɏ�����U������ꏊ�������܂��B
�i���n�ł���Ε��p�����b�܂ꂽ�i�ς���荞�ޑ��ł���A�Z��n�œ����𗯎�ɂ��鐶���ł���e���r�����z�u����܂��B
�x�O�ł͐d�X�g�[�u�����ݒu����邱�Ƃ�����܂����A�������u�������W�߂钆�S�v�ɂ܂Ƃ߂�Ƌ��z�u���₷���Ȃ�܂��B
���ԂɌ��炸�A���̑��̋����ɂ����ʂ��āA�������W�߂�|�C���g�����Ƌ�Ԃ��������܂�܂��B�����n��������ƋC�����ǂ��Ȃ�܂���ˁB
|
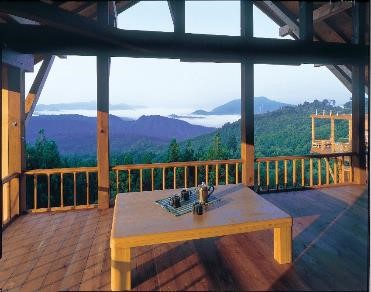
|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�V�j�Ɩ�
��r�I�L����Ԃő����̗p�r�����˂镔���ł́A���ꂼ��ɍ���������I�肵�A
�s�v�Ȏ��͕����I�ɏ����ł���悤�������U�Ɩ����̗p���Ă��܂��B���̓_�ŃV���v���ɔz�u�ł���̂��_�E�����C�g�ł��B
�u���U�z���v�̂悤�ɁA�Ɩ����ʓI�ɕ��U������Ɠ_�����ɏƓx�̃o���c�L��s�v�ȉe����邽�ߕs�����������܂��B
�u�W���z���v�́A�K�v�ȏꏊ�ŏƓx���m�ۂ��Ȃ���V��ʂ���������Ă��ė��z�I�ł��B
�������V�����邽�߂ɂ́u�����ƏW���v���d�v�ŁA�{���ɖ��邳�̕K�v�ȏꏊ���������A
�z�u���邾���œ_�݂��Ă����_�E�����C�g���_�E���E�ʂƂȂ�������`�œV��ɉf���o�����̂ł��B
�V�䂾���łȂ��g�̎���̂��̂��������邱�ƂŔ������A�Ƃ܂ł͂����܂��A��������Ƃ��ċC�����̂������̂ł��B
|


|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�W�j��ƌ�
���C�g�A�b�v�����łȂ��A�������܂߂������I�Ȏ��_�ł̏Ɩ��v�悪�K�v�ł��B
�Z�܂��́u���v�Ɓu�O�v���Ȃ����C�e�B���O�ŕt�����l�̍�����Ԃ��������܂��傤�B
�n�ʂ����Ƀ��C�g�A�b�v����X�|�b�g���C�g�́A�u�n�ʁv���Ǝ˂ł����A�������֓����Ă��܂��܂��B
���̏ꍇ�́A����������X�|�b�g���C�g�����𗎂��āu���v�u�n�ʁv�u�ǖʁv���L�͈͂ɏƎ˂���ƌ��ʓI�ł��B
�O�ǂɃX�|�b�g���C�g���ݒu�ł��Ȃ����́A�����p���j�o�[�T���_�E�����C�g�ƃX�p�C�N���̍L�p�X�|�b�g�̑g�ݍ��킹�Œ�����C�g�A�b�v����ƁA
�]���ȉe���o�����ɏ_�炩���u���v�u�ǖʁv�����C�g�A�b�v���܂��B
�u���v�u�n�ʁv�u���ʁv�̂R�������Ƃ炷���Ƃɂ���āA���邭��������i�����o�����Ƃ��ł��܂��B
��Ɍ��������邾���Ŗ����̋�ԂɂȂ�c�ō��ł��ˁB�Ăɂ͗��݂Ȃ��������肷��̂������ł��ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�X�j�d�X�g�[�u
�Ζ���@�����������ɕ��������������悤�ɂȂ����d�X�g�[�u�B
�g���������łȂ��A�S�n�悳���^���Ă���܂��B
�d�X�g�[�u�́A���ʂ̃K���X�ʂ����łȂ����͂̓S����������o������t�˔M��
�X�g�[�u�O���̕\�ʉ��x�ɂ���Ēg�߂�ꂽ��C���㏸���ēV��ɓ�����A�����Ɋg�U����Η��Œg�߂��܂��B���ׂĂ����n����ʒu�ɐݒu����̂����z�I�ł��B
�����Ŗ��n�E�X�ł́A�I���W�i���d�X�g�[�u���J���A����Ă����Ē����Ă���܂��B�d�X�g�[�u�ɕ�����g�߂邾���łȂ��A�����@�\�����Ă�����Ƒ��@�\�Ȑd�X�g�[�u�ɂȂ��Ă���܂��B
����ς�j�̃��}���ł���ˁ`�B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�O�j���d�Ɛ_�I
���d�Ɛ_�I�́A�ǂ�������邭�����ȏꏊ���ǂ��Ƃ���Ă��܂��B���˓�����������ʂ����ǂ����C�����Ȃ��ꏊ���K���Ă��܂��B
�@����n��ɂ���ĕς��܂����A�����쑤���ނ����ʒu�ɔz�u���邱�Ƃ������悤�ł��B
�s��̂��̂ɋ߂Â��Ȃ��A��K�͒ʘH�╔���������A�w�ʂɕ����������Ă��Ȃ��A������������ɂ��Ȃ��A�Ȃǂ̔z���������邱�Ƃ�����܂��B
�_�I�̏ꍇ�́A�o�����ȂǒʘH�̏���������ق����ǂ��ƌ����Ă��܂��B
���ƂɋA��ƕ��d�E�_�I�ɂ�������������̂ł����A�p�����œ�����ɔz�u����Ă��܂����B
���낢��ƍl�����Ă���̂��ȁA�Ǝv���܂����B�������̍�����Ȃ��Ȃ��������̂ł���ˁB
|
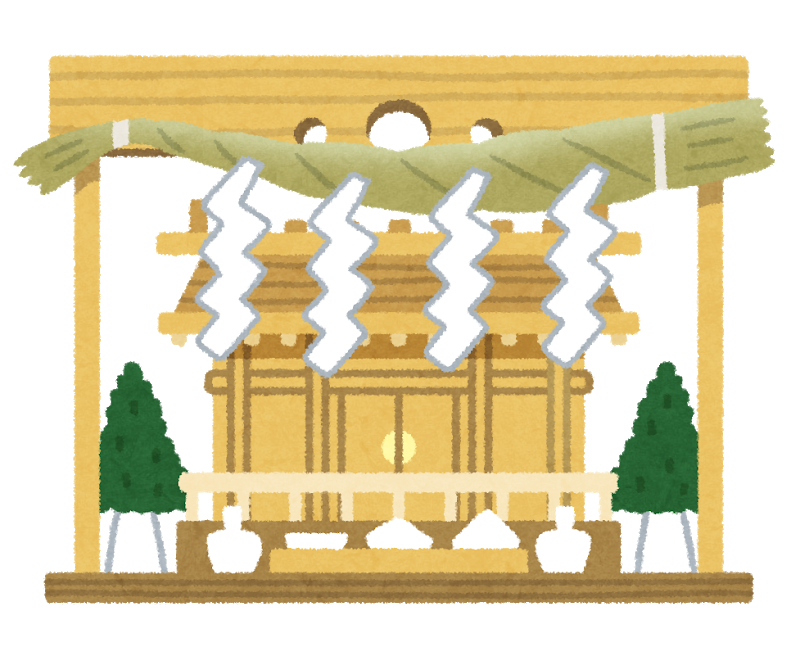

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�P�j�A�[�g�ƃf�U�C��
�A�[�g�ƃf�U�C���A���t�ɂ���ƑS���Ⴂ�܂����A��i�Ȃǂ��݂�ƂȂ��Ȃ���ʂ����Ȃ������肵�܂���ˁB
�f�U�C���́u��낤�Ƃ�����̂̌`�Ԃɂ��ċ@�\��Y�H���Ȃǂ��l���č\�����邱�Ɓv�v�悩�琬�肽���A
�A�[�g�́u����ȑf�ށE��i�E�`���ɂ��A�Z�I����g���Ĕ���n���E�\�����悤�Ƃ���l�Ԋ����A�y�т��̍�i�v��葽���̊���ƁA��菭�Ȃ��l�����琬�藧���Ă���悤�ł��B
�A�[�g�ɂ́A�V������Ȃ肤��X�L����K�v�Ƃ��A�f�U�C���͒N�ł��K�����邱�Ƃ��\�ł��B
���ɂ̓S�b�z��s�J�\�̂悤�ȓV�˓I�Ȃ��̂͂Ȃ��̂ŕ`�����Ƃ͋��ł����A
�f���炵����i���ς邱�Ƃ͎����ɂƂ��ĂƂĂ������h���ɂȂ�̂ŐϋɓI�Ɋӏ܂������Ǝv���܂��B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�Q�j��
�������ɂ߂�Ƃ��A�d�v�ȃ|�C���g�́A�u���@�̃o�����X�v�Ɓu�F�̒��a�v�ł��B
���@�̃o�����X�Ƃ́A�ŗǂ̔��ɋ߂Â��邽�߂̈ʒu���r���Ȃ���͍��������邱�ƂȂ̂ł��B
�����A�Y��Ȃ��̂���������̂�g�ݍ��킹�Ă��X���������߂��܂�������Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤�B���ꂼ���g�ݍ��킹���Ƃ��������Ȃ�悤�ɁA�傫�������菬����������A����������Z��������A�o�����X���K�v�ɂȂ�̂ł��B
�F�̒��a�Ƃ́A��a���̂Ȃ��F�g���ł��B
���R�E�ɂ���z�F�Ɉ�a�����o������̂͂���܂���B�l�H�I�Ɏ��������ꂽ���̂Ɉ�a�����o����z�F�������ł��B���_���ƕ\�����D�ސl�����܂��B
���a�̂Ƃꂽ��Ԃɍ���̉Ԃ���֒u���ƁA�^����ɂ��̉Ԃɖڂ��D���Ă��܂��܂��B
��a�����@�m���r�����邱�ƂŁA���g�����ӂ���Ԃ����邱�Ƃ��ł��A�F�̒��a��ۂ̂ł��B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�R�j��ґ���
�f�U�C������̑匴���͕K���u��ґ���v�ł��B
�Ⴆ�A�`�Ƃ�����̈Ă����Ő���ɓ����Ă��f�U�C���̒�`�u�l���č\������v�ɂ͂Ȃ�܂���B
�������f�U�C����Nj�����Ȃ�A����ɔ��W�������a�āA�^�t�̂b�Ă��l���o�����Ƃł`�Ă̂Ƃ��ɂ͖������������������o���܂��B
����Ɏ��t����ΎO�����̉��s�����o�ĕ��͋C���ς��܂��B���̏u�ԂɁh�����Ɨǂ��Ȃ�ɂ͂ǂ������炢���H�h�Ƌ^�╄�����������A���Ɍ����č\�����������Ƃ����d�v�Ȃ̂ł��B
���Ђ��A���[�����Ă���������f�U�C���쐬�����q�l�ɒ��Ă����܂��B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�S�j������
���E�ōł��������䗦�A�Ñ�M���V���ȗ��u�_�̔�v�Ƃ��Ă����I�Ŕ������䗦�ł���ƌ����Ă��܂��B
���R�E�ɂ����Ă����ڂ�����̂����A�Ԃт�̐��A�t�̐������ɂ�������������邱�Ƃ��ł��܂��B
�g�����v�₽���Ȃǂ̓���I�Ȃ��̂���A�G�W�v�g�̃s���~�b�h�A�p���e�m���_�a�Ȃǂ̌��z���A���i���U�ɂ�������͎g���Ă���̂ł��B
���i���U�ɂ܂ʼn����䂪�g���Ă���Ƃ͒m��Ȃ������ł��ˁB
�C�Â��Ȃ������ŁA�����ȂƂ���Ɏg���Ă�̂�������Ȃ��ł��ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�T�j�����
�O��̃R�����ʼn�����ɂ��ď����܂������A����͔����ɂ��ď��������Ǝv���܂��B
�����ɔ���B�Ȃ�ƂȂ����t����t�����v�������т܂��ˁB
�����Ƃ́A������Ɠ��l�ɂ悭�m���Ă��܂����A���{�Ŕ��˂����䗦�Ȃ̂ł��B
���{�̎��̋K�i�u�`�Łv�u�a�Łv����\�I�Ȃ��̂ł��B�`�S���ɂ���Ƃ`�T�ɂȂ�A�܂�Ԃ��Ă������䗦���ۂ����������ƕ֗��������˔����Ă��܂��B
�@�����̋����A�d���A�����G�́u���Ԃ���l�}�v�ɂ�����䂪�g���Ă��܂��B
������E�����Ƃ��ɔ������䗦�ł����A���{�l�ɂƂ��Ă͔����̂ق����e���݂₷���̂�������܂���ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�U�j�]���y
�]���y�N���X�́A���̓�������ɂ���ėl�X�ȐF���ɕω����܂��B
�����ӂ̑��z���獷�����ތ��̊p�x�E�ʂɂ���Č��������ς��A
���͋C�̈Ⴄ���o�����Ă���܂��B
�Ö��Ƃ̕����ł����Ă��}�b�`���܂��B��̕��͋C�������݂̂���F�˂��A
���炮��Ԃɂ��Ă���܂��B�]���y�N���X�̐F���Ɩ��C�ނ̐F���������ɒ��a���A
��藎��������ԂɂȂ�̂ł��B
���z�̌��A�Ɩ��̌��A���ň�����������ɂȂ�̂͂ƂĂ����͓I�ł��ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�V�j�ǂ��֎q
�������g�̑̂̑傫���ɂ����������傫���A�[�������������Ɋ|�S�n���ǂ��ł���ˁB
�ł����A��ʂɂ���Ă͎g���������K�v�ł��B
�I�t�B�X��w�Z�Ȃǂ̏�ʂł́A�_�炩������֎q�́A�s����Ȃ��ߖ��ӎ��Ɏp����ς���p�x�������Ȃ�W���͂��U�����Ă��܂��܂��B
�Ƃł��낮�\�t�@���L�w�ɂȂ�ӂ�ӂ�̂��͔̂��₷���A���Ƃ����đ̂ɂ҂����荇���M�u�X�̂悤�Ȃ��̂����܂�悭����܂���B
�w������̌X�Ίp�x��110�x����ꍇ�͖���t���������ǂ��ł��傤�B
�_�C�j���O�`�F�A�͑������Ə�̂̊p�x��95�x�ȏオ�ǂ��A���ʂ̍�����38�p�O��A�I�|�������Ă�̂����z�ł��B
���Ђł́A���E�I�|�E�u�b�N�X�^���h�������V�R���C�ނ��g�p�������b�L���O�`�F�A������舵���Ă��܂��B������肵���|�S�n���ƂĂ������ł��B
���Г����ɒu���Ă���܂��B��낵��������|���S�n��̌����Ă݂Ă��������B
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�W�j�j�t���ƍL�t��
�j�t���͂܂������L�т鐫���������A�L�t���͊��������Ȃ����Ă����蕡�G�Ɏ}�����ꂵ���肷�鐫���������܂��B�O�������łȂ������\�����傫���قȂ�܂��B
�j�t���̑g�D�͒P���ŁA�唼�̎����90���ȏオ�����ǂƂ��������琅���z���グ�Ċ�����}�t�ɑ���ǂō\������Ă��܂��B
���čL�t���͕��G�ŁA���𑗂�͓̂��ǂŖ��x����͖̂ؕ��@�ۂ��s���܂��B
���̑��ɂ��זE���x���ł��ꂼ���ڂ��Ⴂ�܂��B
�p��Őj�t���́usoft wood�v�L�t���́uhard wood�v�ƌĂ�Ă��܂��B
�����ł����ꂼ��Ⴄ�͕̂s�v�c�ł��ˁB
|

|
|
|
�����N�Ɩ��C�ށi�P�X�j�g�[�^���R�[�f�B�l�[�g
�������͕�����������Ƃ������d�v������ł��傤���B
�ǎ��Ƃ̐F������������A�����Ă���Ƌ�̔z�u�������肳�܂��܂��Ǝv���܂����A
���C�ރC���e���A�̃v���ɂƂ��āA���ʂȐԏ��̓������ނɂ́A�����ԏ��̉Ƌ���Ƃ��������ꊴ�͌��������Ƃ͂ł��܂���B
�j�t���̑f�ށA���C�ނƒ��a�̂Ƃꂽ�ǎ��A���C�̑��݊����o���������A
�ł��������������Ɗ���������̋�ԁB
�ו��ɂ܂Łh�����h���ӎ����邱�ƂŒ��a�̂Ƃꂽ�R�[�f�B�l�[�g���ł���̂ł��B
���̕����������̋�Ԃɏ����ς��Ă݂悤���ȂƎv���܂��B
|

|
|
